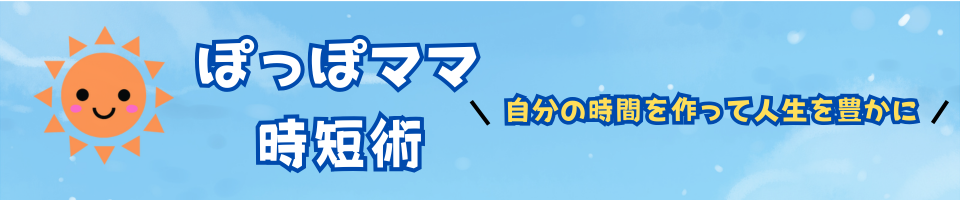- 洗濯物がなかなか乾かない
- 部屋の湿気が気になる
- カビや結露の対策をしたい
育児や仕事に忙しいワーママにとって、家事の効率化は重要な課題です。湿気対策は、家族の健康や快適な生活環境を維持するために欠かせません。この記事では、ワーママに最適な除湿機の選び方を詳しく解説します。記事を読めば、自分の生活スタイルに合う除湿機がわかります。
» 仕事も家事も効率が大事!ワーママの1日のスケジュール管理方法
除湿能力はもちろん、省エネ性能、静音性などが重要なポイントです。衣類乾燥機能や空気清浄機能などの便利な機能もあるため、状況に合わせて検討しましょう。
除湿機の種類

除湿機の主な種類は、以下のとおりです。
- コンプレッサー方式
- デシカント(ゼオライト)方式
- ハイブリッド方式
- ペルチェ方式
コンプレッサー方式
コンプレッサー方式の除湿機は、高い除湿能力が特徴です。冷媒を圧縮・冷却して湿気を取り除くため、広い空間でもしっかり除湿できます。温度が低い環境でも稼働でき、長時間の使用に適しています。除湿水の再利用が可能で、耐久性の高さも特徴です。消費電力が比較的高く、動作音が高い傾向にある点は考慮しましょう。
寒冷地では凍結の可能性があるため、注意してください。メンテナンスは比較的容易で、忙しいワーママでも扱いやすい除湿機です。広い空間や長時間の使用が必要な場合は、コンプレッサー方式の除湿機がおすすめです。
デシカント(ゼオライト)方式

デシカント(ゼオライト)方式は、吸湿剤を使って空気中の水分を吸収します。低温・低湿度の環境でも効果的に除湿できるため、冬場や寒冷地での使用に適しています。デシカント方式の除湿機は、コンプレッサー方式と比べて軽量コンパクトで持ち運びが容易です。設置場所の選択肢も広がります。
静音性に優れており、就寝中や作業中でも音を気にせずに使用可能です。吸湿剤再生のために熱を使用するので、電気代はコンプレッサー方式より高めになります。メンテナンスが比較的簡単で、長期的な維持管理に手間はかかりません。衣類乾燥に使用できる点も、デシカント方式の特徴です。
除湿と同時に温風を出すため、洗濯物を効率良く乾かせます。冬場や梅雨時期など、外干しが難しい季節に重宝します。
» 洗濯物を早く乾かす!天候に関係なく効率的に乾かすコツを紹介
ハイブリッド方式
ハイブリッド方式は、コンプレッサー方式とデシカント方式の両方の特長を兼ね備えた除湿機です。最大のメリットは、季節や湿度に応じた除湿方法を自動的に選択できることです。低温時はデシカント方式を使用し、高温時はコンプレッサー方式を使用します。
ハイブリッド方式により、消費電力を抑えながら高い除湿性能を実現できます。年間を通じて安定した除湿効果が得られ、衣類乾燥や結露対策など多目的に使用できる点がおすすめです。大型で重量があるため、移動するときは注意してください。
メンテナンスには、コンプレッサー方式とデシカント方式の両方の知識が必要です。ハイブリッド方式の除湿機は初期費用が高めですが、長期的に見れば経済的です。購入の際は使用環境を含めて検討しましょう。
ペルチェ方式
ペルチェ方式は、半導体素子を使用した、小型で軽量な除湿機です。冷却面で結露した水滴を集める仕組みを採用しています。温度差が小さい環境での効果が高く、梅雨時期や湿度の高い季節に活躍します。消費電力が低く省エネ性に優れている点から、電気代が気になる人におすすめです。
ペルチェ方式はメンテナンスが容易で静音性が高く、持ち運びも簡単です。除湿能力は比較的低く、大きな部屋での使用には向きません。寝室やクローゼットなど、狭い空間での使用がおすすめです。ペルチェ方式の除湿機は、手軽に使える便利な製品です。動作音が静かで、小さなお子さんがいる場所でも安心して使用できます。
除湿機の選び方

除湿機を選ぶときは、以下のポイントを考慮しましょう。
- 除湿能力
- タンク容量
- 省エネ機能
- 静音性
- お手入れのしやすさ
除湿能力
除湿能力は1日の除湿量(リットル)で示されます。部屋の広さに合わせた選択が大切です。湿度が高い地域や梅雨時期では、より高い除湿能力が求められます。衣類乾燥機能付きの除湿機を使う場合も、除湿能力が高い製品がおすすめです。除湿能力が高いほど、電気代が上がる傾向があります。
自動運転機能付きの機種を選ぶと、効率的に除湿でき、電気代の節約が可能です。季節や用途に応じて除湿能力を調整できる機種もあり、年間を通して使いやすくなります。除湿能力は、温度や湿度などの使用環境によって変動し、表示された能力と異なる場合があります。使用環境も考慮に入れて選びましょう。
タンク容量

2.5〜5リットルのタンク容量の除湿機が多く販売されています。子育て中のワーママにとって頻繁な水捨ては面倒なため、大容量のタンクがおすすめです。タンク容量が大きいと、除湿機全体が重くなるデメリットもあります。小さな容量のタンクなら、軽量で移動しやすく便利です。
2階以上で使用するときは、軽量な小容量タイプも検討しましょう。1日の除湿量に合った容量の選択がポイントです。水捨ての手間を減らしたければ大容量を、移動のしやすさを重視する場合は小さい容量を選んでください。自動排水機能付きの除湿機を選べば、タンク容量を気にする必要がありません。
省エネ機能
省エネ機能を使うと、必要なときに必要な分だけ除湿ができ、無駄な電気代を抑えられます。自動運転機能は、湿度を感知して自動で運転を調整してくれる機能です。タイマー機能も省エネに役立ちます。就寝中や外出時など、必要な時間だけ運転するため、電気代を節約できます。
インバーター制御を搭載した機種も、省エネ性が高い点が特徴です。除湿量に応じて出力を調整するため、効率的に運転できます。省エネ設計された除湿機を選ぶと、長期的な電気代の節約につながります。家計にやさしい除湿機を選びましょう。
静音性

静音性は、除湿機を選ぶときの重要なポイントです。就寝時や作業時に使用する場合には、運転音が静かな製品を選びましょう。一般的に30〜50デシベル(dB)の範囲が静音とされています。デシベル表示で騒音レベルを確認し、自分の生活環境に合った静音性の製品を選びましょう。
静音モードや夜間モードがある機種の選択もおすすめです。デシカント方式の除湿機はコンプレッサー方式より静かで、振動や共振音の少ない機種も静音性に優れています。静音性と除湿能力はトレードオフの関係にあるため、バランスを考慮して選んでください。
» 夜に洗濯物を干すメリット・デメリットとは?
実際の使用感を知るには、ユーザーレビューを参考にしましょう。静音性は数値だけでなく、実際の使用環境での感覚も重要です。
お手入れのしやすさ
簡単にお手入れができる除湿機を選ぶと、日々の家事の負担を軽減できます。簡単に取り外せるフィルターならこまめに清掃ができ、除湿機の性能を長く保てます。タンクの取り外しと排水のしやすさも、日々の使用で大切なポイントです。片手で持ち運べる軽量なタンクや、排水口の位置が使いやすい設計の除湿機を選ぶと便利です。
» 仕事と家事を両立したい!コツや役立つサービスについて解説
本体の拭き掃除がしやすい製品も、お手入れの手間を減らせます。
除湿機の便利な機能の選び方

除湿機には以下の便利な機能があります。
- 衣類乾燥機能
- 空気清浄機能
- タイマー機能
- 自動停止機能
機能が多いほど高額となるため、日々の生活スタイルや家族構成、住環境を考慮して選びましょう。
衣類乾燥機能
衣類乾燥機能を使うと、洗濯物を効率的に乾かせます。送風機能で衣類に風を当てて乾燥させ、温風機能で乾燥時間を短縮します。衣類のニオイを抑える消臭機能や、室内干し特有のイヤなニオイを防止する機能も便利です。花粉やほこりを除去してきれいな状態で乾燥させられるため、天候に左右されずに洗濯物を乾かせます。
» 洗濯時間を短縮!洗濯におすすめの時間や効率よく行うコツを紹介
衣類乾燥機能は、梅雨や冬場の室内干しにおすすめです。衣類の種類に合わせた乾燥モードを選択でき、デリケートな衣類の乾燥も安心です。乾燥の完了を知らせるアラーム機能もあるため、忙しい家事や仕事中にも状況を確認できます。衣類の量に応じて運転時間が自動調整される機種なら、電気代を抑えられます。
衣類乾燥機能は、家事の負担を軽減して時間を有効活用したいワーママにおすすめです。
空気清浄機能

空気清浄機能があると、室内の空気をきれいにしながら湿気を取り除けます。HEPAフィルターや活性炭フィルターにより、花粉やハウスダストの除去が可能です。PM2.5対策にもつながり、細菌やウイルスを低減します。空気清浄機能は、アレルギー症状がある人におすすめです。
多くの機種では、空気の汚れ具合を数値やランプで表示する機能が付いています。自動運転モードを使うと、空気の汚れを感知して自動的に運転を開始するため便利です。静音設計の機種を選ぶと、夜間も気にせず使用できます。フィルター交換時期をお知らせする機能がついた製品もあり、メンテナンスも簡単です。
空気清浄機能付きの除湿機を選ぶと、1台で2つの役割を果たします。
タイマー機能
タイマー機能を活用すると、電気代の節約や生活リズムに合わせた湿度管理が可能です。就寝時や外出時に自動で運転を開始・停止したり、子どもの就寝時間に合わせて静かな運転モードに切り替えたりできます。衣類乾燥機能と組み合わせての、効率的な洗濯物の乾燥も可能です。
毎日同じ時間に運転する繰り返しタイマー機能を備えた機種もあるため、季節や生活リズムに合わせて設定しましょう。スマートフォンアプリと連携して遠隔操作ができる機種もあり、外出先からでも除湿機の操作が可能です。タイマー機能は、忙しいワーママの強い味方です。
自動停止機能

自動停止機能は、除湿機を安全かつ効率的に使用するために欠かせません。タンクが満水になると自動的に運転を停止するため、水漏れを防げます。留守中や就寝中の使用に便利です。一部の機種では、満水ランプやブザーで知らせる機能が付いています。
転倒時に自動停止する機能が備わっている製品もあるため、小さなお子さんがいる家庭でも安心して使用できます。
除湿機の選び方に関するよくある質問
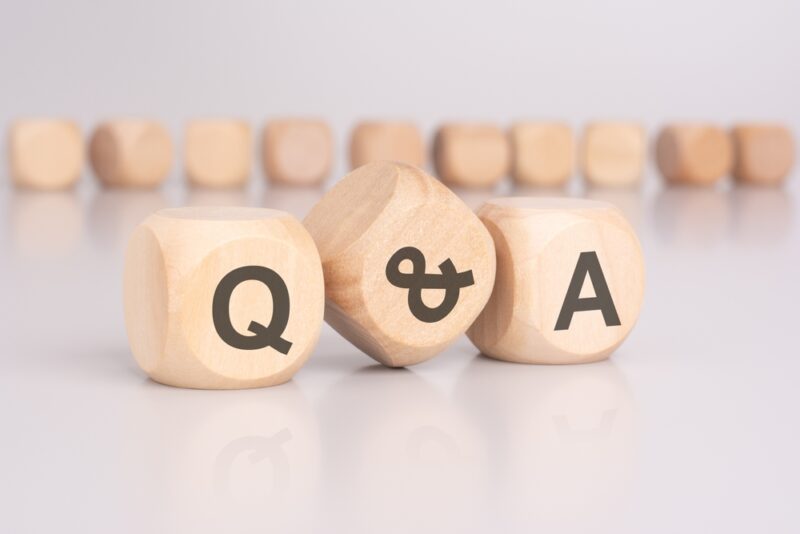
除湿機の選び方に関するよくある質問をまとめました。
除湿機を使うとどれくらい電気代がかかる?
除湿機の電気代は、使用時間や機種によって異なります。一般的に1日8時間の使用で、10〜30円程度です。コンプレッサー式は1日約20〜30円、デシカント式は1日約10〜20円かかります。月間と年間の電気代の目安は、以下のとおりです。
- 月間:約300〜900円
- 年間:約3,000〜10,000円
電気代を抑えるには省エネモードを活用し、湿度設定を高めにしましょう。タイマー機能の使用もおすすめです。除湿機は、エアコンの除湿機能よりも電気代を抑えられる点が特徴です。衣類乾燥機能を使用すると電気代が高くなります。使用環境や機種によって電気代は変動するため、自宅の状況に合わせて使用しましょう。
除湿機とエアコンの除湿機能の違いは?

除湿機とエアコンの除湿機能には、大きな違いがあります。除湿機は湿気を専門的に取り除く機器ですが、エアコンは冷房機能に除湿機能が付随しています。除湿機の最大の特徴は、室温を上げずに湿度を下げられる点です。
エアコンの除湿は室温も下げるため、梅雨時期や冬場など寒さを感じやすい季節は除湿機の方が快適に使用できます。使用場所によっても特性が異なり、除湿機は狭い空間や密閉空間での使用に最適です。エアコンは広い空間の除湿に効果的です。低温時の性能も異なります。
除湿機は低温時でも動作しますが、エアコンの除湿機能は効率が落ちます。除湿機とエアコンの除湿機能の違いを理解し、自宅の環境や用途に合わせて適切な機器を選びましょう。
フィルターの交換頻度はどれくらい?
フィルターの交換頻度は、3〜6か月ごとが目安です。使用環境や頻度によって異なるため、注意が必要です。交換時期を判断するポイントは、以下を参考にしてください。
- メーカーの推奨交換時期
- フィルターの汚れ具合
- 空気清浄機能の有無
フィルターの寿命を延ばすためには、掃除機でのクリーニングが効果的です。交換時期を過ぎると、除湿効率が低下します。交換用フィルターのストックを用意しておくと、突然交換が必要になっても慌てずに対応できます。定期的なフィルター交換は、除湿機の性能を維持するためにも重要です。
まとめ

除湿機には4つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。選ぶときは、除湿能力やタンク容量、省エネ機能、静音性、お手入れのしやすさを考慮してください。便利な機能として衣類乾燥や空気清浄、タイマー、自動停止などがあります。電気代やメンテナンス方法も考慮しながら、自分の環境に合った除湿機を選びましょう。