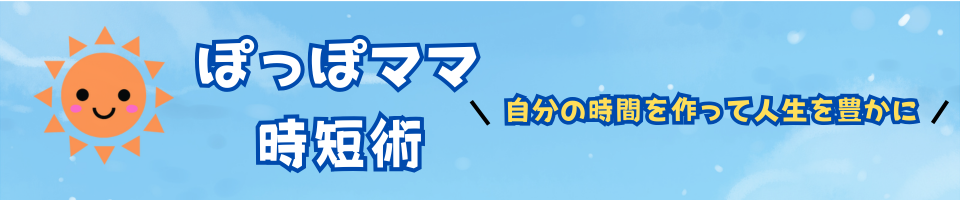夫婦共働きだと、子育てがうまくできないと悩んでいる人は多くいます。負担が夫婦の片方に偏ってしまうと、信頼関係が崩れ、子どもの成長にも悪影響を及ぼしかねません。本記事では、共働きの子育てが大変な理由や、子どもの成長時期別の悩み、ストレス軽減方法、おすすめのサービスを解説します。
記事を読めば、共働きの夫婦による子育ての悩みを軽減し、より充実した家庭生活を送れます。共働きでの子育てを乗り越えるには、パートナーとの協力が不可欠です。共働きでもうまく子育てをする方法を学び、実践していきましょう。
共働きの子育てが大変な理由

共働きの子育てが大変な理由は、以下のとおりです。
- 時間が制限される
- 育児と家事の負担が偏る
- パートナーとのコミュニケーションが不足する
- 育児と仕事の両立が難しい
- プライベートな時間の確保が難しい
時間が制限される
仕事と育児を両立するワーママにとって、時間の制約は課題の1つです。朝晩は、子どもの送迎や習い事のスケジュールに追われ、自由に使える時間が限られます。急な残業や出張への対応が難しくなり、仕事面でも制約を受ける場合があります。家事や育児に時間を取られ、自分の時間の確保が困難になりがちです。
睡眠不足や子どもとの触れ合いの時間が減少し、休日も育児に追われやすくなります。子どもの病気や緊急時の対応が難しい点も問題の1つです。
» 仕事も家事も効率が大事!ワーママの1日のスケジュール管理方法
育児と家事の負担が偏る

育児と家事の負担の偏りは、夫婦間の不公平感を生み、妻のストレスや疲労の原因です。妻の仕事上のキャリア形成にも悪影響を及ぼす可能性があります。日本は性別の役割分担意識が強く、多くの家庭で妻が家事や育児を、夫は仕事中心の生活を送る構図が見られます。負担が妻に偏る原因は、以下のとおりです。
- 夫の家事・育児参加不足
- 妻のワンオペ育児の増加
- 夫の育児休業取得率の低さ
- 夫の長時間労働による家庭への関与不足
妻の完璧主義も負担を増やす一因となります。「自分がやらなければ」と思い込むため、負担が増えてしまいます。問題を解決するには、家庭内の役割分担の見直しと夫婦間での協力が必要です。
» 共働きの夫婦は必見!家事分担の見直しと夫婦円満のコツを解説
パートナーとのコミュニケーションが不足する
仕事や家事に追われ、夫婦間の悩みや不満を共有できず、子どもの成長や教育方針の意見交換が不足してしまいます。コミュニケーション不足が続くと、ストレスや疲労が蓄積し、感情的になりやすくなります。相手の気持ちや状況がわからないと、目標や価値観を確認できません。
結果的に信頼関係が崩れ、夫婦関係や家族の絆に悪影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
» ワーママが疲れたと感じる瞬間と疲れる原因、対処法を解説!
育児と仕事の両立が難しい

時間の制約や責任の重さにより、育児と仕事のバランスを取ることが難しくなります。子どもが急に熱を出したり、保育園や学校の行事に参加したりすると、仕事のスケジュールを急遽変更しなければなりません。仕事に集中できず、パフォーマンスが低下し、キャリアの停滞や昇進機会が減少する場合もあります。
職場での理解不足や偏見も、両立を難しくする要因の1つです。育児休業後の職場復帰の難しさや、子育て中の人に対する配慮の不足が、ワーママの負担を増大させています。結果的に、心身の疲労が蓄積し、子どもとの時間を十分に確保できなくなります。
» 仕事と子育ての両立が難しい理由と両立させるポイント
プライベートな時間の確保の難しさ
仕事と家事、育児に追われる毎日の中で、自分のための時間の確保は困難です。直面する問題は、以下のとおりです。
- 休日も家事や育児に追われる
- 趣味や交流の機会が減る
- 自己投資の時間が確保できない
- 十分な睡眠が取れない
- プライベートな時間の確保が難しい
十分な休息や自己ケアの時間が取れないと、ストレスが蓄積し、バーンアウトのリスクが高まります。夫婦の時間が減ると、コミュニケーションが不足し、両者の関係に悪影響を及ぼす場合もあります。自分の健康管理や美容ケアの時間が不足すると、自己肯定感が低下し、仕事のパフォーマンスにも影響を与えかねません。
» 休日無気力症候群になってない?休日何もしたくない原因と対処法
【子どもの成長時期別】共働きの子育ての悩み

共働きの子育ての悩みを、以下の子どもの成長期別に紹介します。
- 乳児期(0~1歳6か月)
- 幼児期(1歳6か月~3歳)
- 幼児後期(3~5歳)
- 小学校低学年(6歳~)
乳児期(0~1歳6か月)
乳児期は、子育てと仕事の両立が難しい時期です。乳児期には、以下の悩みが多い傾向があります。
- 夜泣きや授乳によって眠れない
- 離乳食の準備や食事介助の時間が確保できない
- 予防接種や定期健診のスケジュールが調整できない
- 急な発熱や体調不良による仕事の調整ができない
課題を乗り越えるには、パートナーと協力し合うことが欠かせません。夜間の授乳を交代で行ったり、保育園を一緒に探したりすると、育児と仕事の両立がしやすくなります。離乳食は、休日にまとめて作り置きすると、平日の負担を軽減できます。予防接種や健診は、早めに予定を立てて職場に伝えておきましょう。
子どもの急な体調不良に備え、勤務先と事前に相談し、柔軟に対応できる環境を整えておくことも大切です。自分の時間を少しでも確保し、周りの助けを借りながら乗り越えてください。
幼児期(1歳6か月~3歳)

幼児期は子どもの成長が著しく、親にとっても新たな課題が生まれる時期です。コミュニケーション能力が向上する一方で、自我の芽生えや反抗期の始まりにより、親子のやり取りが難しくなります。トイレトレーニングの開始や食事の好き嫌いが顕著になるため、基本的な生活習慣の定着には、時間と忍耐が必要です。
運動能力も向上し、活発に動き回るため、目が離せない場面が増えます。集団生活や友達との関わりが増えると、感情のコントロールが難しくなり、トラブルが起きやすくなります。想像力が豊かになる時期のため、遊びを通じた学習ができる適切な環境づくりが必要です。
幼児期の子育てには多くの課題がありますが、子どもの成長を実感できる喜びが大きくなります。子どもの自立心を尊重しながら、適切な指導を心がけ、基本的な生活習慣の形成に根気強く取り組みましょう。
幼児後期(3~5歳)
幼児後期になると、子どもの自我が強くなり、言うことを聞かない場面が増えます。成長の一環でもあるので、焦らず対応しましょう。幼児後期に多い悩みは、以下のとおりです。
- 友達関係のトラブル
- 行事や準備物の増加
- 食事の好き嫌いなどの問題
子どもの質問が増え、答え方や対応に悩む場面も多くなります。感情表現も豊かになるため、気持ちの起伏が激しくなり、対応に戸惑うことも増えます。兄弟がいる場合は、争いやねたみが顕著になる場合もあるため、子ども一人ひとりの個性を尊重しながら公平に接しましょう。
小学校低学年(6歳~)

小学校低学年になると、子どもの生活環境が大きく変わります。新しい環境での適応や学習面でのサポートが必要になるため、親の悩みも増えていきます。小学校低学年の時期に直面しやすい課題は、以下のとおりです。
- 学校生活への適応
- 宿題の習慣づけ
- 放課後の過ごし方
- 学校行事と仕事の両立
- 友人関係のトラブルやいじめへの対応
子どもが新しい環境に適応できるサポートの実施が大切です。学習面では、宿題の習慣づけや基礎学力の定着を促す必要があります。仕事で疲れていると、負担が大きくなるため、自分自身の心身のケアも行ってください。小学校低学年の時期は、子どもの成長が目に見えてわかる楽しい時期でもあります。
悩みも多いですが、子どもの成長を喜び、家族で協力して乗り越えましょう。
共働きの子育てのストレスを軽減する方法

共働きの子育てのストレスを軽減する方法は、以下のとおりです。
- パートナーと役割分担を見直す
- タスクの優先順位をつける
- スケジュール管理を徹底する
- 自分の時間を確保する
パートナーと役割分担を見直す
家事や育児の負担を適切に分担すると、お互いの負担が軽減され、より良い家庭環境を築けます。効果的な分担方法は、以下のとおりです。
- 得意分野や空き時間を考慮して分担する
- 定期的に分担を見直して調整する
- タスクリストを作成して進捗を共有する
- 子どもの成長に合わせて役割を変更する
役割分担を見直す際は、お互いの負担を理解し、感謝の気持ちを伝えましょう。柔軟に助け合える関係を築くと、より効果的に分担ができます。夫婦間でコミュニケーションを密に取り、不満をためない工夫も重要です。互いの仕事や予定を尊重し合いながら、家族全体でバランスの取れた生活を送れます。
必要に応じて外部サービスの利用も検討しましょう。家事代行サービスや配食サービスなどを活用すると、家事の負担を減らせます。
» 共働きの家事分担の妻と夫のよくある不満と解消方法を解説!
タスクの優先順位をつける

限られた時間の中で効率的に物事を進めるためには、重要度と緊急度でタスクを分類する必要があります。「今すぐやるべきタスク」と「後回しにできるタスク」を明確にしましょう。子どもの成長に関わることや仕事の締め切りは優先順位を高く設定し、家事は必要最低限に絞るのがポイントです。
子どもに任せられるタスクを増やすと、家事の負担を軽減できます。タスクリストを作成し、視覚化すると、毎日の作業を効率化できます。優先順位は固定せず、定期的に見直して状況に応じて調整しましょう。適切な優先順位付けを行うと限られた時間を有効活用でき、育児や仕事、自分の時間のバランスが取れます。
スケジュール管理を徹底する
スケジュール管理の徹底は、共働き家庭の生活をスムーズに進めるうえで重要です。徹底したスケジュール管理により、仕事と家庭の両立がしやすくなります。効果的なスケジュールの管理方法は、以下のとおりです。
- 家族全員の予定を一元管理する
- 仕事・家事・育児の時間帯ごとに細かく分ける
- 子どもの学校行事や習い事を早めに把握する
スケジュールを立てるだけでなく、定期的な見直しと調整も必要です。家族会議を開いて予定を確認し、必要に応じて調整しましょう。緊急時の対応策をあらかじめ決めておくと、不測の事態にも対処できます。余裕を持ったスケジュール作りを心がけ、To-doリストを作成して優先順位をつけるのも効果的です。
» 仕事と家事を両立したい!コツや役立つサービスについて解説
自分の時間を確保する

心身のリフレッシュのために、定期的に自分だけの時間を持つことが大切です。忙しい日々の中でも、朝早い時間や子どもの就寝後の時間を活用すると、自分の時間を確保しやすくなります。週末にリフレッシュの時間を設けたり、友人や趣味の集まりに参加したりするのも効果的です。
家事や育児の合間に短時間でもリラックスできる時間を設けるのもおすすめです。パートナーに協力を得ると、自分の時間を確保しやすくなります。
» 時間は作れる?ワーママが自分の時間を作る方法を具体的に解説
共働きの子育てにおすすめのサービス

共働きの子育てを支援するサービスは、以下のとおりです。
- 地域の子育て支援センター
- 保育園や学童保育
- ファミリーサポートセンター
- 病児保育
地域の子育て支援センター
地域の子育て支援センターは、子育て中の親子が気軽に集える場所であり、さまざまなサポートを提供しています。支援センターの特徴は、以下のとおりです。
- 育児相談や情報交換ができる
- 子育て講座や親子イベントに参加できる
- 専門スタッフによる育児アドバイスが受けられる
- 同じ年齢の子どもを持つ親同士で交流できる
おもちゃの貸し出しサービスや、一時預かりサービスを提供している施設もあります。無料または低料金で利用できるため、経済的な負担も少なくて済みます。
支援センターを活用すると、育児の負担を軽減し、地域の子育て情報を得やすくなります。同じ立場の親同士で情報を交換すると、新しい発見や解決策が見つかる可能性があります。多くの施設が平日の日中に開設しているので、仕事の合間を縫って利用する工夫が必要です。
保育園や学童保育

保育園や学童保育は、共働き家庭にとって欠かせないサービスです。子どもの年齢や家庭の状況に合わせて利用でき、仕事と育児の両立を支える役割を果たしています。保育園は0歳~就学前の子どもを預かり、学童保育は小学生を放課後に預かる施設です。
両施設とも、子どもの成長をサポートしながら、保護者が安心して働ける環境を整えています。利用条件や料金は地域によって異なります。人気のある施設では、待機児童の問題が発生する場合があるため、利用する際は早めに申し込みましょう。
一時保育や緊急時の預かりに対応している施設もあり、急な仕事や用事の際にも活用できます。保護者の就労時間に合わせた利用が可能なため、自分の働き方に応じて選択してください。
ファミリーサポートセンター
ファミリーサポートセンターは、育児の援助を受けたい人と提供したい人をマッチングするサービスです。地域の実情に応じたサービス内容となっているため、共働き家庭には心強い支援を受けられます。利用には会員登録が必要で、料金は地域によって異なります。事前に面談や説明会への参加が必要です。
サポート会員は子育て経験者が多く、研修制度も整備されているため、安心して利用できます。急な依頼にも対応可能な場合があり、突発的な事態にも役立ちます。市区町村や社会福祉協議会が運営主体となっているため、信頼性が高い点も特徴です。
病児保育

病児保育は、子どもが病気やケガをした際に、仕事を休めない保護者をサポートするサービスです。専門の看護師や保育士が常駐し、子どもを預かります。利用には事前登録が必要な場合が多いものの、当日キャンセルが可能な施設もあります。対象年齢は0歳〜小学校低学年までです。
施設の種類には、医療機関併設型や保育所併設型、単独型があり、通常の利用時間は約8時間です。食事やおむつは持参が必要なので注意してください。感染症の種類によって利用制限がかかる場合があります。利用料金は自治体により異なりますが、多くの場合、通常の保育サービスよりも高めに設定されています。
まとめ

共働きの子育てには課題が多いですが、適切な対策を講じると乗り越えられます。時間的制約や負担の偏りなどの問題に直面した場合は、パートナーと役割分担を見直し、優先順位を付けましょう。子どもの成長段階に応じた対応も重要です。
ストレスを軽減するには、スケジュール管理の徹底や時間の確保が役立ちます。地域の支援センターや保育サービスなどの外部リソースも活用して、子育てと仕事の両立をしやすくしましょう。
夫婦で協力し、互いを支え合うことで、子育てはかけがえのない喜びをもたらします。大変なときこそ、家族の絆を深め、子どもとともに成長していきましょう。